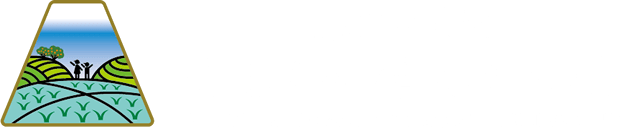空港から望む美しい自然の邑
牧之原市の北東部に位置し、明治時代に本間賢三により本間隧道(ずいどう)が整備され、古くから農業の活性化を図ってきました。
現在ではお茶やお米、レタスやみかん等様々な農作物が栽培されており、多くの水資源を活用した、田畑の発展が目覚ましい地域です。
平成21年には、富士山静岡空港が開港し、世界へ繋ぐ邑(むら)としても注目されています。
また、美しい環境資源として多くのホタルが生息し、毎年5月から6月頃にホタルの鑑賞会をおこなっています。
世界でも珍しい三種のホタル(ゲンジホタル、ヘイケホタル、ヒメホタル)を見ることができる貴重な里は、地域の方による生態系保全活動により守られています。

地域街づくりの推進
市の地域街づくり事業にいち早く取り組み、発展を目指して、Facebookによる坂部のPRをおこなっています。ゆるキャラ「さかべっち」も作成され、地域の活性化のため活躍しています。
また、榛原里山の会の取り組みで、地元の坂部小学校の生徒に環境の学習会を開催したり、田植え体験を開催したりと、地域の資源の大切さを教えています。

石雲院・展望デッキ・飛翔軒
「石雲院(せきうんいん)」は、勝間田城主から寺領を寄進され、康正元年(1455年)に創建されました。
勝間田氏の菩提寺(ぼだいじ)として、また今川氏、武田氏、徳川氏と、有力な大名に庇護され、全国に800を超える末寺を数える、由緒ある古寺です。
山門、総門、参道の丁石、龍門の滝の彫刻など、建築や彫刻技術に優れており、市の指定文化財になっています。緑深い山中にあり、散策するだけで心が洗われるような境内です。
また、石雲院展望デッキが静岡空港の隣接地にあり、展望デッキでは地元の有志の方たちが「飛翔軒」を運営しています。
売れ筋はその日の朝に採れた野菜で、新鮮さと値段の安さから、土・日曜限定営業にもかかわらず多くのリピーターがおり、土曜の朝には主婦らが列を作ることもあります。

心のふる郷、葉梨西北
新東名高速「藤枝岡部IC」からわずか10分で行ける邑(むら)。そこに広がるのは、どこか懐かしい農村の原風景。
川に舞うホタル、山にはみかん、お茶畑。そして、アーモンドの花が、邑(むら)に新しい風を呼び起こします。
5月の中旬から6月初旬まで、葉梨川の滝見橋から川沿いに、約1.5キロにも渡りホタルの舞う姿を楽しめます。さらに上流の上大沢では、6月中旬までホタルの舞を楽しむことができます。
毎年5月の終わり頃に開催されるホタルまつり。「白ふじの里」を会場に、屋台や地元農産物を楽しめます。葉梨川沿いには手作りの竹灯篭が並びます。
同じ葉梨川沿いでは、春にはアーモンドの花が咲き誇り、秋には彼岸花の真っ赤な絨毯を楽しめます。
四季折々の自然が溢れる葉梨川を守っているのは、全戸参加の草刈作業。地域のみんなが集まることで、葉梨川の自然とともに、地域コミュニティも守っています。

アーモンドの里づくり
一社一村しずおか運動への取り組みとして、株式会社明治東海工場と協働し「アーモンドの里づくり」を進めています。株式会社明治から贈呈された苗木を葉梨山水会で維持管理し、訪れる人が楽しめる里づくりを進めています。
年に1回、アーモンドの花が咲く3月に開催するアーモンドまつりで、植樹者が苗木の手入れをおこなっています。お祭りで提供されるアーモンド餅は人気の一品です。

アンテナショップ「白ふじの里」
地元で開発した「しょうがシロップ」と「しょうが醤油」。地元産しょうがを使用し、しょうがのおいしさがギュッと詰まっています。
商品は、葉梨川沿いにある地域活性化施設「白ふじの里」で購入できます。この施設ではほかにも、そば打ち体験や味噌づくり教室、農業体験などを行い、地域の魅力を積極的に発信しています。
【「白ふじの里」ホームページ】
http://shirafujinosato.cocolog-wbs.com

汽笛鳴り、蛍舞い、心が和む抜里
大井川中流域に位置し、お茶を主体とした農業が中心に営まれています。緑豊かな自然環境に恵まれた地域で、広大な茶園内を邁進するSLは、鉄道ファンのみならず多くの人を魅了します。
ふじのくに美農里プロジェクト活動に取り組み、植栽等による美しい景観を維持しています。また、ホタルの生育による生態系の保全活動にも力を入れ、ホタルのシーズンになると地域内外からたくさんの人が足を運びます。
大井川鉄道に乗車した旅行客が思わず、途中下車したくなるような、自然が豊かで綺麗に整備された集落です。
地域の方が主体となり、上手川沿いで毎年6月中旬に「ホタル鑑賞会」が開催されています。会に向けて草刈りや清掃はもちろんのこと、幼虫の育成もおこなっており、毎年たくさんのホタルを見ることができます。
周辺に電灯が無いため、懐中電灯が必須になりますが、真っ暗な分、ホタルの光が美しく、幻想的な光景をみることができます。

川根茶ぬくり園
土地改良事業により綺麗に区画整理された茶園では、乗用型茶刈機が活躍し、邑(むら)の主要農産物であるお茶が、効率よく生産されています。近年では、急須で飲むお茶以外にも、ドリップ使用のお茶に取り組み、さらなる需要拡大を目指して頑張っています。
川根茶ぬくり園は、抜里地区8工場を再編したお茶工場です。外観は従来の茶工場のイメージを一新し、オーストリアのシェーンブルン宮殿をモチーフに、たいへんモダンな建物となっています。
加工設備も最新の製茶機械を導入し、1日約7tの荒茶が仕上がります。周辺への環境面を配慮しての集埃、防音装置はもちろん、安心、安全面でも最大限の注意を払い、トレーサビリティーシステム、二重の異物除去装置も設置されています。

パワースポット「五輪さん」
勝負事にご利益があるパワースポットとして、様々なスポーツチームや受験生から信仰を集めている場所です。
戦国時代には、狼煙台だったと伝えられており、毎年9月1日の縁日にはお菓子等が配られ、多くの参拝者でにぎわいます。

斜面に広がる茶畑と温かな住人
梅ヶ島大代地区は、静岡駅から安倍川沿いに車で約80分北上した、標高720mの中山間地域です。集落に入るとすぐに、緑いっぱいの茶畑と森林の香りに包まれます。清涼な湧き水のおかげで、おいしいお茶や山葵の産地となっています。
大代道を上り切ったところには、青い空と緑の茶畑が一面に広がっています。
茶畑は邑(むら)の人たちによって美しく管理され、その合間に邑(むら)の家々がとけ込んでいます。こうした風景に、林道を歩く人々も思わず足を止め、邑(むら)の人たちに語りかけます。

お茶としいたけと山葵の里
お茶は梅ヶ島のブランド「まるうめ茶」として出荷されます。その他、しいたけ、山葵が主要産物です。
邑(むら)では、しいたけ狩りやしいたけバーベキューができ、地区で育てた野菜を使ったさまざまな郷土料理を味わうことができます。
しいたけハウスでは、標高700m以上になる山の頂上で原木椎茸を栽培しています。原木椎茸は、ナラやクヌギの木で育てた「木の子」で、味も香りも絶品です。
お客さんは、しいたけを自分で収穫して、その場で炭火で焼いて食べることができます。

大学生と地区の未来を語らう邑
12世帯35人の邑(むら)である大代に、静岡大学農学部の学生が週末や夏休みに訪問して、茶畑や水道(みずみち)や道路の管理などを邑(むら)の人たちと共同でおこなっています。
静岡大学生は、空き家を借りて宿舎として使い、夜には宿舎で邑(むら)の人たちと地区の未来について語り合います。

畑に咲いた富士山に登りませんか?
鎌倉時代後期の地頭、南条時光公(地元住民は敬意を払い「南条さん」と呼ぶ)が、この地の里づくりに尽力したことに敬意を払い、住民が一丸となって景観を守り、創る活動を中心とした地域づくりに励んでいます。
住民の手で、遊休農地の解消や富士山の眺望スポットを作ることを目的とした取り組みが進められ、3・4月は菜の花、7・8月はコスモスやヒマワリ、10月には“富士山アート”も見事なクッションマムやソバが富士山を彩ります。
また、農地の環境保全活動、廃棄物の出ない環境にやさしい豆腐づくりにも取組んでいます。
毎年10月になると見ることができる“富士山アート”では、耕作放棄地解消と景観形成のために植栽したクッションマムが満開を迎え、畑に見事な富士山が浮かび上がります。これなら、足腰に自信がなくても富士山に登ることができると多くの見物客が訪れます。

「大豆プロジェクト」と食イベント
廃棄物の出ない環境にやさしい豆腐づくり「大豆プロジェクト」。
その取組で収穫された大豆を活かそうと、常葉大学富士キャンパス社会環境学部によって“まるごとふじとこ豆腐”ほか、大豆加工品として商品化されています。
大豆の旨味を捨てることなく“まるごと”味わえる魅力的な逸品です。
「南条の里 蕎麦まつり」(平成24年から毎年冬に開催)では、耕作放棄地解消と景観形成のために植栽したソバを地域の方々に振る舞います。また、常葉大学富士キャンパス社会環境学部も参加し、協働活動において作った、“まるごとふじとこ豆腐”や味噌の販売もおこなっています。
毎年2月には、地域の酒造会社(牧野酒造、富士正酒造)と牧場(土井ファーム)等で行われる”上野の里まつり”に出店し、”まるごとふじとこ豆腐”も南条の里ブースで販売しています。

農地の保全で拡がる協力・調和
農業者、自治会、学校花の会、防災会などの大同団結により「南条の里農地保全会」が発足され、様々な活動に取り組んでいます。
また、常葉大学富士キャンパス社会環境学部とは「大豆プロジェクト」を通じて「一社一村しずおか運動」を進めています。
「南条の里農地保全会」が主催し、平成24年より開催する「南条の里 蕎麦まつり」は、地域住民が集い、舞踊の披露や常葉大学生との交流を育む新たなにぎわいの場となっています。

竜ヶ石山を抱えた恵み豊かな地
西四村地区は、旧引佐町に位置し、浜松市中心部から車で約50分の中山間地域にある農村地帯です。
集落東側に神宮寺川が流れ、傾斜の急な農地では主としてみかんが栽培されています。
また、隠し田として作られた白橿(しらかし)の棚田や軽便鉄道の路線跡等もあり、歴史を感じさせる景観が見られます。

竜ヶ岩洞をはじめとした見所
邑の北部には、鍾乳洞で有名な竜ヶ岩洞があります。
新東名高速道路が開通してアクセスが良くなったことから、県内外から多くの観光客が訪れています。また、旧引佐町内には、奥山方広寺や横尾歌舞伎資料館、井伊谷宮、龍潭寺等、歴史的文化財が数多くあり、それらとの相乗効果により地域の活性化が図られています。

棚田の復田で潤いのある里づくり
白橿(しらかし)の棚田では、平成19年から「里山元気もりもり隊」が保全活動を続けており、耕作放棄された棚田の復田に取組んでいます。
地域内外から参加者を募り、田植えなどを行っています。
また、平成25年度から「ふじのくに美農里プロジェクト」に取組み、農村環境保全を積極的に行っています。

地域をあげて環境保全
平成20年より、「一宮の水と環境を守る会」として、地域の農業用水等の資源を守り、農村環境の保全向上に取り組む活動が行われています。
平成23年からは再生した耕作放棄地を一般市民に開放し、農業に挑戦してもらおうと「一宮ふれあい農園」が始まりました。
また、とうもろこしの収穫や田植えなどの農業体験、生き物調査などは、幼稚園からシニアクラブまで幅広い年代の地域住民が活動に参加しています。

新東名開通でますます活気づく市場
遠州浜名湖鉄道の遠江一宮駅では、毎月「まちあい朝市」が開催され、地元で採れた新鮮な野菜の他、漬物や惣菜などの食品、手工芸品も売られています。
また、新しい玄関口として新東名遠州森町パーキングエリアにスマートインターが設置されたことで、一宮への来訪者が増え、宮の市や明神通などの地元農産物の直売所や食事処では、地元住民と来訪者との交流がにぎわいを見せています。

伝統が受け継がれる十二段舞楽
毎年4月には、国指定重要無形民俗文化財となった十二段舞楽が、小國神社にて演じられます。
十二段の舞うち六段を、地元の小学校に通う子どもたちが舞子として舞います。
舞楽の指導や稽古をとおして、地域の伝統文化のみならず、舞の技と心が次の世代へと継承されていきます。

里山の自然の復活
雑草が生い茂り、人も入らず、道路や水路がどこにあるかも分からなくなっていました。
しかし、水路の土を取り除き、田んぼには木道を設置し、山には階段を作り、花壇や緑木を植えるなど、人が再び入れるよう整備されました。
今では、里山の自然がよみがえり、トンボやカブトムシ、セミや小鳥が身近に見られるようになりました。

地域社会(コミュニティ)の場
毎年、4月には鯉のぼりを上げ、夏休みには自然観察会を開催し、里山に親しんでいます。
また、地域住民、親子の触れ合いの場として、農園、花壇作り、夏にはバーベキューが行われています。会員と地域の子どもたちによるしめ縄作りなど、地域の伝統を子どもたちに継承する活動も行われています。

野外学習の場
小学生、幼稚園・保育園の野外学習の場として、四季折々の自然観察や昆虫採集や幼稚園の遠足、バードウォッチングが行われています。
また、ハイキングコースや駐車場も整備され、大人と子どもの交流の場になり、年々多くの人が里山を利用するようになってきています。

市東部に広がる茶園・水田風景と梅園
掛川市東部に位置し、国道1号の南北に茶園と水田地帯が広がります。
東山口地区では、農地総合開発事業により、茶園62.6ha、水田26.2haが整備されました。
また、平安時代の貴族である菅原道真の詠んだ和歌に名前を由来する「掛川梅園 こちの里」があり、3月には240本の梅の木が満開になります。

地場野菜の販売が人気の「梅まつり」
毎年3月上旬には、「掛川梅園 こちの里」で「梅まつり」を開催し、1,500人が訪れます。
梅干しや梅酢などの加工品のほか、イチゴやお茶、地場野菜などの販売所が人気です。
また、フリーマーケットも同時に開催されています。

小学生が農業体験、地域共生の農地活用
東山口と西山口の2つの地区が合同の取り組みとして、遊休農地の積極的な利活用を目指してサツマイモやソバが栽培されています。
また、地元小学校と協力して、田植えから稲刈りまでの稲作体験や、茶摘み体験が実施されています。

田原「水車の里」
水車の里は、田原公民館裏に位置します。
平成16年度から平成20年度まで、田原小学校6年生と一緒に毎年1基、計5基の水車を作成しました。
平成23年9月21日の台風15号により全壊してしまいましたが、「卒業生の心のこもった水車をなんとかしたい」という思いから、有志の方々が半年で全て修理しました。
四阿をはじめ環境を整備し、水車の里として親しまれています。

いわた田原の歴史さんぽみち
田原ふるさとかるたのウォークマップは、邑全域を楽しめるコースになっています。
旧東海道の松並木や、徳川軍と武田軍が戦った大日堂、天然記念物の大楠がある須賀神社を見てまわることができます。

地名の多様な農産物
川根本町は、大井川から立ち上る川露や山露が茶葉を日光からさえぎり、昼夜の温度差が多く、良質なお茶が育つ理想の環境となっています。
加えて、町内では数少ないまとまった平坦地を持つ地名地区は、多様な農産物の産地となっています。川根茶はもちろんのこと、川根本町唯一のお米栽培。ハウスではしいたけ栽培。最近ネギの路地栽培も始まりました。

ユーモアあふれる「案山子コンテスト」
2年に1度、9月下旬から10月上旬の稲穂が鮮やかに色づく頃、ずらりと並んだ個性的でユーモア溢れる案山子を見ることができます。
これは、住人のふれ合いを大切にしている地名区民が、秋の豊作に感謝し、健康に良いとされる笑いを目的として、「地域で取り組む生涯学習事業」の一環で開催しているものです。
みのりの秋に地名を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてください。

日本一短いトンネル
大井川鐵道大井川本線の「地名駅」北側には、全長約10mの日本一短いトンネルがあります。
トンネルは、線路上をまたいでいた藤枝市瀬戸谷~川根を結ぶ、川根索道(貨物ロープ-ウェイ)につるされた荷物が、列車に落下するのを保護するために建設されました。
現在はその索道は廃止され、トンネル部分のみが当時の面影を残しています。

四季に合わせて美しい自然がたくさん
山あり川あり、そして田んぼあり、の日本の原風景。
それでも、清水の街場から車で30分、静岡の中心部からでも1時間で来られる場所です。
近年、近くで絶滅危惧種の「ミヤマシジミ」の生息も確認されています。
また、清水森林公園やすらぎの森には「西里の滝」があり、隠れた滝の名所でもあります。

充実のお食事処と農産物加工体験
【ショップ「como」特製ジェラートが話題】
地元で栽培されたハックルベリーや抹茶・赤ジソなどを使ったジェラート、地元のNPO複合力の畑でとれた薬膳を入れ込んだタイカレーなどを販売しています。
【山の幸満載の定食】
食事処「たけのこ」では、山里でとれる野菜や蕎麦などをたくさん使った各種定食がそろっています。
【お土産はこちら「笑味の家」】
山里の野菜、その日に打った蕎麦やうどん、その他農産物加工品も季節に合わせて並んでいます。
【農産物加工場「ぬくもりの家」】
蕎麦打ちやこんにゃく作り、餅つきまで指導付きで行えます。グループや団体に好評です。

鳥のさえずりのなか入るお風呂は最高
農作業や散策をした後に入るお風呂は何物にも代えがたいです。
特に露天で源泉かけ流しはおすすめ。ゆっくり入るとストレスも解消します。

名瀑「白糸の滝」と富士山を彩る農村景観
富士山世界文化遺産の構成資産である「白糸の滝」は地域の宝です。そして、区画整理事業により蘇り、「平成棚田」と命名した農地は、日々の営農や地域内外の人々の協働活動により富士山の四季の変化に彩を添えています。
平成棚田を散策するノルディックウォーキングは、案内看板を6か所、道標を21か所設置して、「白糸の滝」や、隠れた名所「朝日滝」を訪れるコースが整備されています。
※案内看板設置場所:白糸の滝駐車場、朝日滝、狩宿駒止の桜、工藤祐経の墓近辺、そば処白糸庵、フジヤマ病院入口向かい
※パンフレット配布場所:白糸の滝駐車場の案内所

“地域の風土”“人の技”が光る自慢の食
「平成棚田」で収穫されるお米は、富士山の麓の美味しい空気、清涼な湧水に恵まれた素晴らしい環境の中で収穫され「白糸コシヒカリ」として販売されています。
また冬場の水田を活用した「水かけ菜」は、地域自慢の特産品です。
さらに、地元住民の婦人組織で経営する手打ちそば処「富士山白糸庵」は、常連客や観光客が訪れ、“手作りの味”が好評です。
※富士山白糸庵:火曜定休日

邑の宝で繋がる地域内外との絆
毎年8月に文殊堂で行われる文珠祭典では、手筒花火が次々と上がり保存会の花火師たちの華麗な舞が見ものです。
親水公園にアジサイの花が咲く頃の鱒釣り大会では、子どもや里帰りした家族たちの歓声が上がります。
また、「ふじのくに美農里プロジェクト」にいち早く取組み、遊休農地の解消や景観形成、更には「三椏和紙発祥の地」の伝統を守るべく、小学生に三椏の栽培や和紙づくりを地域学習を通じて継承しています。地区外の方との友好親善を通じた農村振興を目指し、平成21年から「一社一村しずおか運動」にも取り組んでいます。

四季折々の作物がなる肥沃な土地
大賀茂は、中心市街地に隣接する、山々に囲まれた静かな農山村集落です。
河川流域から山の中腹までの一帯で、米、野菜、柑橘や柿などの季節に応じた農業風景が見られます。
5~6世紀頃からの遺跡が点在することからも、太古から肥沃な土地で豊かな営みがあったことを物語っています。

継承される伝統文化と自然環境
大賀茂では、地元有志団体が主体の文化活動や環境保全等の交流機会を通じて、地域内の人的なつながりが保たれ、伝統的文化の継承が図られています。
特に、文化行事の開催においては、保育園児から高齢者まで幅広い年齢層で地域総出の参加が見られます。

れんげ祭をはじめとした田園地帯の活用
4月末、南伊豆東海バス「金山」バス停付近のれんげ畑で開催される「大賀茂れんげ祭」は、地域活性化を目的とした住民手作りのイベントで、地場産品等の露店や宝探しなどのゲームが行われます。
会場となる田園一面にれんげが咲き、上空に掲げられる多数の鯉のぼりと相まって、のどかでほのぼのとした光景が、懐かしい雰囲気を醸し出しています。この活動は、約15年に及び年中行事として定着したこともあり、周辺地域からも大勢の方が来場します。
会場として使用される田園地帯では、冬にクリスマスのイルミネーションが施される他、2011年には、下田青年会議所が稲作体験事業を実施するなど、新たな活用の取組が創出されています。

浮島ひまわりランド
浮島地区センターから南へ200m離れた位置にある浮島ひまわりランドは、隣接する2箇所の休耕田を埋め立て、地域住民によって整備されました。
地域の家庭で苗を観察しながら育て、6月初旬に植栽し、7月中・下旬に開花します。満開のひまわりと富士山の遠望を楽しむことができ、多くの方がカメラを持参して集まります。ひまわり写真撮影会やコンサート等のイベントも開催されますので、日程は浮島地区センター(055-968-1322)へお問い合わせください。ひまわりや浮島の景観・行事を撮影した写真コンテストも開催しており、応募作品は浮島コミュニティまつりに展示されるとともに、受賞作品はまつりの中で表彰されます。
ひまわり開花後は、種を採取し、秋に搾油してひまわり油を精製します。これを使ってコミュニティまつりでさつま揚げなどの試食も提供されています。冬から春にかけては菜の花が栽培され、1年を通じた景観形成を図っています。

古城の湧水活用イベント
浮島地区には、愛鷹山の麓を走る県道(通称根方街道)沿いに多くの湧水箇所が点在し、生活用水や水田の水源として活用されてきました。また、地区内には戦国時代の武将北条早雲が伊豆攻めの旗上げをした古城「興国寺城址」があり、発掘や整備が進められています。その城内にも自噴する湧水井戸があり、古城の歴史遺産と農業資源である湧水を守り育てる活動として、水路を整備しました。春には「興国寺城跡で遊ぼう」と題し、地産の煎茶や抹茶の試飲と焼き芋のイベントを開催し、たくさんの方が参加します。

貴重な生態系を子どもの世代に
浮島地区の水田地帯は、かつて狩野川と富士川の砂嘴(さし)によって海水が囲い取り込まれた地形で、江戸時代には浮島沼や広沼と呼ばれる湿地帯が広がっていました。放水路整備などで深田は徐々に解消されてきましたが、今でも貴重な湿性植物「ノウルシ」が自生しています。
浮島地区では、水田の美しい景観を保持するため、「一社一村しずおか運動」による企業からの協力を得ながら、休耕田の草刈り等、生態系と景観の維持に努めています。また、子どもクラブを組織し、自然観察会、ひまわりの植え付け、トンボ採り合戦、野鳥観察、野草を食べる会、もちつき大会など年間を通じた野外活動を行いながら、浮島の自然と農業を活かした子育てで、貴重な生態系の恵みを子どもたちに伝えています。とりわけ、夏の終わりの夕刻に、水田の芦原にねぐらを求めて数万羽のツバメが大空を群舞する「ツバメのねぐら入り観察会」は、子どもたちの心にふるさとを刻み込みます。