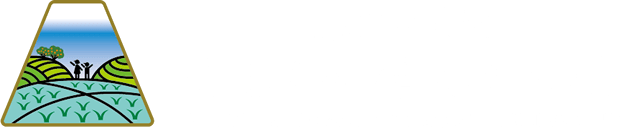ヒガンバナ花街道
伊東市十足地区は周囲は山に囲まれていますが、比較的平坦な地形で長閑な田園風景が広がっています。例年9月のお彼岸の頃から10月にかけての2週間ぐらいの間、地域の皆さんが植えたヒガンバナが見頃になります。十足のヒガンバナは100年以上昔から植えられていたと言われていて、中伊豆と伊東の海を結ぶ街道でもあったこの地を通る人々の目を、古から楽しませてきました。未来へこの美しい景観を引き継ぎ、その景観をもっと多くの人に楽しんでもらおうと地域住民が協力し、土手への植栽など「ヒガンバナ花街道」活動を行っています。
田植えの終わった6月から7月にかけては蛍が舞い、カエルの大合唱も楽しめます。天城山、遠笠山、矢筈山、大室山を望み、穏やかな風景がそこに暮らす人々を優しく包み込んでいます。伊東駅から十足広場行のバスに乗り、「龍雲寺」バス停下車。田んぼの中の遊歩道を歩けば、矢筈山を正面に見ることができます。

有名観光地からハイキング
十足地区は奥野ダムや大室山や「伊豆の瞳」と呼ばれる一碧湖からも歩いて30分ほどです。伊東市のホームページのレジャー情報の中で一碧湖→十足→さくらの里ハイキングコースが詳しく紹介されています。十足はそれほど大きくはない集落ですので、のんびり、ゆったり、歩いてその魅力を満喫して下さい。
十足地区には様々な石仏や史跡が点在しています。集落にある引手力男神社(ひきたぢからおじんじゃ)は大きな神社ではありませんが、慶安5年に修復された記録などが残っている、歴史のある神社です。10月の秋祭りには「翁の三番叟」が奉納されます。民家の片隅、田んぼのあぜ道などに道祖神、馬頭観音、庚申さんの他、少し珍しい神様もいらっしゃいます。歳(せい)の神様(お地蔵さん)には、どんど焼きの炭を塗りつけて真っ黒にすることで、健康祈願をする風習があったそうです。いぼを取ってくれる神様もいらっしゃいます。観光でお近くにお出かけの際は、貴重な日本の原風景・田園風景が残る十足地区にも是非、お立ち寄り下さい。

十足(とうたり)の由来あれこれ
『十足』と書いて「とうたり」と読むこの地域。その地名の由来は諸説あります。
「江戸からの旅人の履いていた10足目の草鞋の緒が切れたから」「山の中で草鞋が10足でも足りないほど険しい場所だから」「十足りるから(自給自足でなんでもそろう)」など、様々です。草鞋の緒が切れるほど歩いて来た旅人も、ここの風景にほっと一息つきながら新しい草鞋に履き替えてまた歩き出したのかも知れません。
十足地域の中を通っている県道351号線沿いには野菜の直売所があり、露地栽培の美味しい野菜が手に入ります。季節によっては珍しい野菜が販売されていることもあります。

雄大なロケーションに広がる梅林
梅林に続く「月ヶ瀬ロード」は集落の間を抜ける道を行くと、広大な敷地に1500本の白梅・紅梅・しだれ梅が植栽された梅林に到着します。2月は梅の花、6月は梅の実が見頃です。梅林内の「天城連山展望の丘」は、雄大な天城の山々を見渡せる貴重な場所です。吉奈~船原を通って、梅と温泉を楽しむハイキングも人気です。

梅の美味しさを楽しめます
梅びとの郷では梅園で収穫した梅を加工した商品を販売しています。体に優しく美味しいと、お土産に好評です。昔ながらの作り方にこだわった梅干しは、まさに「いい塩梅」で、毎年購入に来る人もいます。梅ジャム・柚ジャムは売り切れることもある人気商品。梅シロップは炭酸水やお湯割りにすれば、世代を問わず爽やかな風味を楽しめます。梅シロップ割りの黄金比率は1:4。大人の方は、お酒で割ってハイボール風に。梅アイスも人気です。梅びとの郷で購入できます。6月頃には自分で収穫した梅を使った、梅酒作り体験も企画されます。

空の下で楽しむ音楽
梅林にある天城連山を望むステージでは、秋に十三夜の和楽コンサートが開催されます。月明りの下で聞く地元の天城和太鼓や篠笛、尺八、津軽三味線の演奏はとても幻想的です。
梅林で行われる天城音楽祭は、バンドのライブ演奏を天城連山を照らす夕焼けや星輝く夜空を見上げながら楽しめます。
ある時はしっとり厳かに、ある時は元気いっぱいエネルギッシュに。老若男女が楽しめる音楽イベントが開催されています。

梅まつり・太鼓祭り
梅の花が見頃になる2月に開催される梅まつり。地元の特産品販売、様々なジャンルの音楽演奏、マジックショーやダンス、体験イベントも盛りだくさんです。梅まつりの期間中に静岡県太鼓祭りも開催されます。おなかに「ドドン!」と響く、迫力ある太鼓の演奏を毎年楽しみに訪れる人も増えています。

四季清流桂川に育まれた田園空間
伊豆半島の中心部に位置する修善寺温泉は県下屈指の温泉街で、全国から観光客が訪れます。温泉街を西に進むと、「桂流コシヒカリのふる里」の美しい田園空間が広がります。棚田景観の残るこの地域では、清流桂川を水源として、良質なコシヒカリが栽培されています。また、初夏には清らかな水と空気のなかでホタルの舞う姿も見られます。
豊かな自然、伝統ある温泉街、歴史的資産の3つを兼ねそろえた魅力ある地域です。美しい景観を守るため、地域が一体となって活性化に取り組んでいます。

地域独自の食材でおもてなし
桂流コシヒカリは清流桂川で育まれたブランド米です。平成25年度に「お米日本一コンテストinしずおか」で金賞を受賞しました。安心でおいしい米づくりをモットーとした特別栽培米の栽培が広がっています。
中でも食味スコアが有名ブランド米と比べても引けを取らない水準である「桂流コシヒカリ」は、生産者と修善寺温泉の旅館とが連携し、食材として宿泊客に提供されています。地域で採れたものを訪れたお客様にその場で味わっていただくという地産地消のお手本です。
また、弘法芋や黒米などの地域独自の食材も栽培されています。弘法芋は修善寺温泉を発見した弘法大師にちなんで名づけられ、肉質が密で粘りが強いという特徴があります。黒米はこの地方では薬膳として食べられており、ほんのり甘く香ばしいお米です。

深い歴史が息づく邑
地域周辺には、源範頼(源頼朝の異母弟)の墓や、多くの石碑、寺院が残り、温泉と豊かな自然に深い歴史が溶け込んでいます。桂谷八十八カ所巡拝では修善寺地域に点在する礼所(石碑)を、毎年11月7日~9日の3日間を掛けて巡ります。四国八十八カ所の霊場の土を桂谷の八十八カ所に埋め、石碑を建立しており、四国八十八カ所巡りと同じ功徳が受けられるとして、毎年多くの巡拝者が訪れます。
修禅寺奥の院は、平安初期に弘法大使が開創したと言われています。本寺から桂谷地区を抜けて西に4.6kmほどの所にある奥の院は、若き日の空海(弘法大使)が修業した場所と伝えられています。
春と秋に「春の静寂」「秋の静寂」、冬至には「星まつり」が行われます。
イベント時には、地場野菜や地産食材を使ったお弁当の販売が行われています。

いちごハウスと田園風景
韮山多田地区の風景は広大な水田といちごハウス、富士山の景観がマッチして美しい田園景観を織りなしています。6月初旬の水田の水鏡、8月頃の鮮やかな緑の稲、10月頃の金色の稲穂。四季折々に移ろう田の様子と富士山のある風景は、どれも絵になります。冬から春はいちご狩りを楽しんだ後に雪化粧をした富士山をカメラに収める観光客の方も増えています。寒い季節や朝の早い時間や夕暮れ時は富士山が綺麗に見える事が多いそうです。

ブランドいちごの生産地
多田地区は静岡県のブランドいちご生産の中心地。いちごハウスの中では受粉の役目を担うハチ達が花から花へと飛び交います。きめ細やかに温度管理を行い、安心・安全で品質の良いいちごを生産しています。酸味と甘さのバランスが良く、中までほんのり赤い「紅ほっぺ」は多田地区の特産品の一つで、飲食店や製菓店などの料理のプロからの人気も高いです。
古くから野菜が良く育つ土に恵まれた多田地区では多様な農産物を栽培しています。地域のエコファーマーでは化学肥料、化学農薬に頼らない環境に優しい生産方法で作られた、食味の良い「エコファーマー米」を販売。伊豆トマトの栽培も盛んです。新鮮な農産物はグリーンプラザ伊豆の国で購入できます。詳しくはJA伊豆の国のホームページをご覧ください。

沢山食べて、良く働こう!
多田地区で毎年1月と9月に行われる「山の神講」。江戸後期から続くと言われるこの神事では、山の神様に感謝をし、皆で二杯盛りと呼ばれる山盛りの茶飯を食べます。『沢山食べて、しっかり力をつけて、皆で良く働こう』という意味があり、全員が食べきらないとお開きになりません。現在はご飯茶碗で2杯が一般的ですが、以前はどんぶりで2杯食べていたそうです。地元の小学校6年生も参加して、山盛りのご飯に驚きながらも、地域の心と伝統を継承しています。

伊豆の国いちごまつり
韮山時代劇場では毎年1月、地元産のいちごを使った「伊豆の国いちごまつり」が開催されます。
いちごの販売、いちごを使った体験イベント、地元の皆さんの手作りの品をお得価格で堪能できる「お楽しみ販売品」が人気です。
また、餅まきや大抽選会なども行われ、大変盛り上がります。詳しくは伊豆の国市のホームページをご覧ください

歴史遺産を残す農村環境
世界文化遺産富士山を望む水田地帯の金谷地区は昔ながらの里山の風景が見られ、地域の人々と多くのボランティアにより景観保全に取り組んでいます。神奈川県内で竹林整備等の活動を行うNPO法人「日本の竹ファンクラブ」と、地元団体である韮山金谷の里夢くらぶが協働活動を開始し、主に放置竹林の伐採・整備活動を行います。
間伐する際に発生した竹材を活用して竹灯籠を製作、約4000本の灯籠で江川邸内の竹林、中庭や池をライトアップする韮山竹灯籠まつりを毎年開催。イベントでは、尺八、オカリナ、ハーモニカのコンサートや合唱、竹のオブジェの展示、竹製品やカッポ酒(竹徳利の熱燗)等の販売などが行われ、来場者に竹の素晴らしさと竹林の保護をPRしています。
竹林ボランティアも随時募集中ですので関心のある方はお気軽にご参加ください。

悠久の時と歴史ロマンを感じさせる史跡
邑が誇る国の重要文化財である江川邸は、平成25年9月に世界遺産国内推薦資産に決定した韮山反射炉を造った江川坦庵の住居として、江戸の佇まいを残しています。
江川邸に近接する、ため池「城池」を囲む城池親水公園は、野鳥や魚類の宝庫となっており、地域住民の憩いの場となっています。
さらに、平清盛の継母池禅尼の命乞いによって一命をとりとめ、韮山へ流罪になった源頼朝が、14歳から34歳の旗揚げまでを過ごした蛭ケ小島など、数々の史跡を訪れることができます。

韮山反射炉
韮山反射炉は、代官江川坦庵が手がけ、後を継いだその子英敏により完成しました。反射炉とは、金属を溶かし大砲を鋳造する炉であり、現存する唯一の稼働した反射炉として、平成25年9月20日に世界遺産国内推薦資産に決定しました。

天竜浜名湖線沿いに続く農村の原風景
柿園や水稲栽培などの農用地と森林が調和した中を、天竜浜名湖線が走り抜けていく自然豊かな里地・里山風景が広がります。敷地川沿いの桜並木や、四季折々の自然や眺望の良い獅子ヶ鼻公園のトレッキングコースなどもあり、のんびり散策が楽しめます。四季折々に優しい表情を見せてくれる、農村の原風景が敷地村にはあります。詳しくは豊岡東地区協議会のホームページをご覧ください。

地元の美味しいものを満喫できます
敷地は特産品の柿が有名です。山から吹く冷たい風で干す枯露柿(ころがき)は地域自慢の逸品です。すだれのように吊るされた枯露柿のある風景は、晩秋から初冬にかけての敷地の風物詩です。とても甘いと評判です。食と農の体験施設白壁館では地場産品の購入や、美味しい敷地米の卵かけご飯などの食事ができます。新鮮な野菜、手作り加工品、ころ柿など、敷地村のお土産はこちらでどうぞ。

遠州大念仏蝉しぐれの盆
遠州地方に古くから伝わる念仏踊り「遠州大念仏」(静岡県無形民俗文化財)は毎年8月に開催されます。元亀3(1572)年の三方ヶ原の合戦で多くの死者がでたことから、戦に勝利した家康が両軍の死者の霊を弔うため念仏供養を命じたのが「遠州大念仏蝉しぐれの盆」の始まりと言われています。伝統行事を保存・継承して心豊かなコミュニティの活性化や観光交流を促進しています。

山、水、花に囲まれた自然豊かな里
見渡す限りの菜の花畑は地域内外の人々に親しまれ、訪れた人に美しさと安らぎを与えてくれます。邑には、水稲を中心とした農地と森林が調和した自然豊かな里地・里山景観が形成されています。春先に、地域の南部の桶ケ谷沼南側の畑一面に菜の花が咲く風景は圧巻です。菜の花以外にも、四季折々の自然や景観をハイキングをしながら楽しむことができます。
また、桶ケ谷沼は、日本有数のトンボの生息地としても知られています。絶滅危惧種のベッコウトンボをはじめ、国内に生息するトンボの約3分の1にあたる70種が確認されています。

桶ヶ谷沼ビジターセンター
桶ケ谷沼の自然環境を保全するとともに、自然環境や自然を利用した体験学習活動を行い、自然保護意識の啓発を図ることを目的に設置されました。
入館は無料で、週末には、自然観察会や講演会などの各種イベントが実施されています。桶ケ谷沼は、本州で最東端のベッコウトンボ生息地であり、国内では唯一の安定した多産地といわれています。環境省が公表したレッドリストにおいて絶滅危惧Ⅰ類とされ、自然保護団体や磐田南高校によるベッコウトンボの人工的な増殖計画が進めています。

掛川のシンボル「茶文字」
新幹線や東名高速を走る車窓や空港から見える「茶」文字。昭和7年に東山区住民によって松の木を植生し、管理されてきました。ところが、昭和60年頃に松くい虫の被害に遭い、せっかく育てた木が枯れてしまいました。その跡地に檜を植樹し、現在ではその大きさが縦横約130mです。周辺の雑木の除伐も毎年、地域住民が協力して行っています。 地域のランドマークとなっている茶文字。 春は桜、新茶の季節は鮮やかな緑のお茶畑越しに、冬には雪が舞うこともあり・・・と、季節ごとに美しく個性的な景観を作りだします。「茶」文字が見える向きや大きさで自分の位置がわかるという地元の人もいる、掛川のシンボルです。

世界農業遺産「茶草場農法」は美味しいお茶を育てます
東山地区は、掛川市の粟ヶ岳のふもとに広がるお茶の生産が盛んな地域です。秋から冬にかけて、ススキやササなどの山草を刈り取り、茶園の畝間に敷く農法は、「茶草場(ちゃぐさば)農法」と呼ばれ、平成25年に世界農業遺産に認定されました。茶草場とは、ススキやササが繁茂する半自然草地のことで、茶園周辺に点在しています。毎年、茶草場の草刈りが行われることにより、里山の自然が守られ多様な生物が生息する場となっています。また、茶園に敷かれた山草は良い肥料となり、美味しくて高品質なお茶が育ちます。
【世界農業遺産 静岡の茶草場農法】のページはこちら。

東山を味わい、楽しむ
掛川市東山の粟ヶ岳山麓にある東山いっぷく処では、昔の在来茶を復刻させた在来茶園のお茶(深蒸し茶)を販売しています。東山のシンボルである「茶」文字を用いた、茶文字まんじゅうも人気です。粟ヶ岳山頂に歩いて1時間ほどで行けます。車でも行けますが、道が狭く、カーブが多いです。天気のいい日は山頂から伊豆半島、遠州灘、富士山を望める絶景ポイントですので、お弁当を持ってのハイキングに訪れる人も増えています。
東山地区ではお茶どころらしく、お茶にかかわる祭礼やイベントがあります。毎年元旦には粟ヶ岳の山頂で、初日の出を拝み手揉み茶の実演など湯茶接待があります。4月の栄西禅師供養祭では栄西禅師像前にて献茶と茶接待を行います。9月の山王神社祭典は五穀豊穣と茶業繁栄の祭りで、二輪の山車を引いて祝います。11月は 農業祭で生粋東山茶、こんにゃく、田舎みそ等の販売します。毎月第3土曜日に掛川駅通りで開催される「けっトラ市」にも出店しています。

戦国を垣間見る風景
高天神城は、菊川下流域の平地部からやや離れた北西部に位置し、小規模ながら、山城として堅固さを誇り、戦国時代末期には武田信玄・勝頼と徳川家康が激しい争奪戦を繰り広げました。
優美な山の形から鶴舞城の別称を持ち、国の史跡にも指定されています戦国時代、武田・徳川の合戦の舞台となった高天神の本丸あとから地域の全貌を眺め、戦国ロマンを、体験してはいかがでしょう。

地域のまもりびと
土方地区に工場を置く企業の従業員と農業者や地域住民が参加し、田植え、案山子づくり、稲刈りなどを行い、地域交流を深めています。
小学校では、学校に隣接した田んぼでの田植えの体験学習を20年以上継続して行い、地域農業との交流活動を根づかせています。また、ふじのくに美農里プロジェクトにも積極的に取り組み、農業用施設の共同管理や自治会等と連携した景観形成活動を行い、農地や農業用施設の保全管理のほか、地区内の花壇や緑地帯の手入れも行っています。
素朴と自然の中で、地域の人が観光者が優しく温かく接し会い、明るく元気に動き回るような地域を目指しています。

高天神社例大祭
高天神社は、高天神城跡にあり、かつての高天神城を守護する神社です。祭礼は、毎年3月の最終日曜日に東峰の社に神様が里帰りされる行事として行われます。祭礼は桜の見頃とも重なるため、毎年多くの見物人客で賑わいます。

多彩な農産物と出会いを育む風景
友永地区は袋井市三川地域の中央部にあり、ガラス温室でのメロン栽培、お茶生産、水稲等の多彩な農産物を生産しています。水田は小麦、大豆などの栽培にも利用します。新しい技術を取り入れ、次世代にも残していける農業に取り組んでいます。
新東名開通に伴い、遠州森町PAへ農産物の出店しています。基盤整備された農地での農産物の生産活動から織り成される美しい景観がこの地域の自慢です。その景観を満喫できる農業体験民泊や婚活イベントなども開催されています。「夢の里三川グリーンツーリズム」で四季を通じて県内外から民泊する農業体験を行っています。(お問い合わせは袋井市農政課 電話0538-44-3133)

朝長公を偲ぶ祭り
「源氏の里」は、友永地内の積雲院というお寺に、松尾芭蕉の句に詠まれ、能の演目にもなっている、源朝長公(源頼朝・義経の兄)の墓があることから名付けられました。朝長公を偲ぶお祭り「御礼祭」は袋井市指定無形民俗文化財です。毎年8月15日の夜に行われ、住民が、提灯を持ち歩き、昔の「子守り歌」を歌いながら、無病息災を祈願します。歴史あるお祭りを通し、地域の良さを伝承しています。

豊かな自然と共存する「とうもん」
掛川市・袋井市・磐田市の南部に広がる広大な田園地域のことを「とうもん」と言います。「稲面(とうも)」「田面(たおも)」がその言葉の由来と言われている静岡県内随一の穀倉地帯です。緑の海原、金色の絨毯と、一面の水田が四季折々に魅せる情景も、豊かな自然があってこそ。左の写真はトラクターが耕した後をついて歩くサギたちです。肥沃な土と一緒に掘り起こされた餌を啄ばみに大集合。こんなに多くのサギたちの胃袋を満たす恵みがここにはあります。大自然と農業との共生が織り成す風景は「とうもんの里」の自慢です。
特産物展示スペースなどがある建物はバリアフリーになっています。多目的トイレも完備しています。

農業の面白さ、体験できます
とうもんの里では農業の面白さや、農村文化の良さ、食の大切さを体験講座や刊行誌の発行を通し、伝えていく活動をしています。農業に全く関わった事がない大人も、子供も、一緒になって参加できる体験イベントは年間約100回開催されています。 ジャガイモ掘りやお茶摘み体験、稲刈り体験、籾すり体験、野菜の植え方講座、製茶工場の見学、布ぞうり作り・・・ここではご紹介しきれません。体験イベントなどの情報はとうもんの里のホームページをご覧下さい。

田んぼの生き物を知る体験
とうもんの里一帯には、素晴らしい自然の営みがあります。人の手が程よく入ることで、田んぼに暮らす生き物や自然環境が豊かになり、美しい景観を作り出します。その素晴らしさをみなさんに知っていただきたくて、田んぼの生き物調査を開催しています。自分の手で生き物に触れ、多様な生態系を見る事ができます。
調査に参加してからは、好き嫌いの多かったお子さんがご飯を残さず食べるようになるというお話も聞きます。食育にもオススメの調査です。

趣向を凝らしたかかしがいっぱい!
新野のかかし祭りは、趣向を凝らしたかかしが新野川の堤防沿いに40体以上立ち並びます。来場した人も参加できる人気投票があり、バラエティーに富んだかかし達を前に、お気に入りを選ぶのに迷ってしまうことも。そのユニークで思わずニッコリしてしまう温かい雰囲気に、遠方から毎回足を運ぶリピーターも増えています。毎年10月初旬から中旬まで開催されます。川沿いの遊歩道も環境美化の活動でコスモスやヒガンバナが植栽され、地域の人も訪れた人も花にその目を癒されています。

お土産に地域の特産品を
かかし祭り開催日には、地域の皆さんによる色々な出店があります。新野地域の特産のお茶「御前崎つゆひかり」は食材王国静岡県の認定ブランド「しずおか食セレクション」に認定されています。鮮やかな緑色でやさしい渋みの中に旨みと甘みが引き立つ爽やかな味わいです。新野で収穫されたコシヒカリや、野菜や果物の他、見逃せないのは、かかし祭り限定販売のカカシ煎餅。この時しか手に入らないので、お土産に人気です。また、かかしの立つ遊歩道沿いには、懐かしの手作り竹馬などもあり、子供たちが夢中になって遊びます。

新野左馬助親矩ゆかりの地
新野地区にゆかりのある新野左馬助は戦国時代の武将で、井伊 直政の命の恩人と伝えられています。左馬武神社には、その墓と伝えられる石塔(五輪塔)があります。新野氏の八幡平の城(新野古城)や天ケ谷城平は城址を散策できるハイキングコースになっています。定期的に地域の皆さんでハイキングコースの整備などを行っています。野鳥の声を聞きながら、新野の歴史巡りを楽しめます。お茶の産地でもある新野では、手摘みした新茶を左馬武神社に奉納する献茶祭が4月に行われます。家紋の入った左馬助公どらやきはお土産にも最適です。
田んぼと茶畑の織りなす里山風景
静岡県を代表するお茶と田んぼのコントラストが美しい自然豊かな里山「朝比奈」。
ふるさとを感じさせる、何かほっとさせてくれる景色がここにはあります。御前崎市は、日本屈指の日照量を誇り、太陽の恩恵を最大限に取り入れることができます。朝比奈地区では、牧之原農業用水を利用した茶栽培が大規模に展開されており、新品種「つゆひかり」の導入が積極的に進められています。
「あらさわふる里公園」
地域の交流拠点「あらさわふる里公園」は、山間の懐かしい風景が広がる中に、ビオトープエリア、農業体験エリア、バーベキュー広場、多目的広場、「味工房わらび」、直売施設「ほい!かって家」など様々な施設が充実しています。お花見や茶園ピクニックなどに遠方から多くの人が訪れます。また、園内の棚田では毎年浜岡北小学校の5年生児童が稲作体験をしており、6月に田植え、10月に稲刈りを行っています。園内には桜や梅、ツツジやアジサイなど 四季折々の花が植えられており、1年中いろいろな花が楽しめます。園内には桜や梅、ツツジやアジサイなど 四季折々の花が植えられており、1年中いろいろな花が楽しめます。
バーベキュー広場では、しずおか食セレクションにも認定された「遠州夢咲牛」を堪能できるので、家族で楽しんでみてはいかがでしょうか。

地元農産物は 「ほい!かって家」で
あらさわふる里公園内の直売施設「ほい!かって家(やー)」では、地元の農家が精魂込めて育てた旬の食材を販売しており、新鮮でおいしい野菜を求めて訪れる人々との交流が図られています。
直売施設に並んでいる食材を見ていると、思わず手に取ってしまいます。

「千框(せんがまち)」って?
かつては3000枚もの小さな田んぼがモザイク模様で広がっていた上倉沢地区。千枚の田んぼという意味で「千框(せんがまち)」と呼ばれています。昭和50年代にその数が激減しましたが、かつてのような美しい姿を思い描きながら、地元NPO、学校、棚田オーナー、大学生、企業などが協力して複田、保全活動を行っています。農作業を通して世代・所属を超えた、和やかな交流が生まれています。ムシやカエルが触れなかった子供たちも、いつの間にか生き物と仲良しになっています。中には大人顔負けの生き物博士になっているお子さんも。
先人達が残してくれた、せんがまちの宝を一緒に守っていきませんか。詳しくは棚田いこうよ.netをご覧下さい。

棚田風景あれこれ
田植えの後の水鏡、真夏は鮮やかな緑、稲穂が頭を垂れる頃には金色と、棚田は四季折々に様々な表情を見せてくれます。水の流れる音、キジの鳴き声、カエルの合唱、風が稲穂を揺らす音。耳でも楽しめます。3月には「あぜ道アート」が開催され、揺れる蝋燭の光により幻想的な雰囲気が楽しめます。農作業の合間に空を見上げると、静岡空港を発着する飛行機が見られることも。JR東海道線菊川-金谷間は電車の車窓から棚田が見える珍しい区間です。電車をご利用の場合は、その瞬間をお見逃し無く!

生き物にも温かいせんがまちの邑人
千框では「冬水(ふゆみず)田んぼ」と言って、田んぼを起こす前に水を張ります。土が乾き、田にヒビが入って水が漏れないようにする効果と、生き物の「ゆりかご」の役目があります。
また、千框の棚田に隣接するのは世界農業遺産「静岡の茶草場農法」に欠かせないススキ等が生えた採草地(茶草場)です。こうした自然環境が生物の多様性を育み、冬に水中で産卵する静岡県の絶滅危惧種ニホンアカガエルなども生息する貴重な場となっています。その小さな命を育むため、作業とは関係なく早い時期に水を入れたり、水路にカワニナの餌となるメロンの皮を何気なく1枚入れてあったりと、地元の人々の生き物に対する心の温かさが伝わってくるエピソードもあります。
生き物たちの環境を良くする事が、人間にとっても大切なこと。豊かで多様な生態系をめざし、静岡大学棚田研究会も協力してビオトープを製作しています。

四季折々に表情を変える農村景観
森町南部地域の水田地帯は昭和40年代より、かんがいやほ場整備などの基盤整備が行われた、生産性の高い優良農地です。昭和44年にレタスの指定産地となり以降、スイートコーンが導入され、水稲+レタス+スイートコーンの年3作「水田3倍活用農法」を確立し、年間を通じて休むことなく農業生産活動が行われ、就農する若者が増加しています。四季折々に表情が変わる農村景観は絶景を見せてくれます。

スイートコーンは県外からも大人気
初夏を迎えると当地域の街道沿いにスイートコーンの直売所が立ち並び、早朝から購買客の行列ができます。週末には、評判を聞きつけた県内外各地からのお客さんがやってきます。また、新東名高速道路「遠州森町PA」にて、当地域の特産物を販売しています。地産地消はもちろん、県外にも森町の農産物の美味しさを広めています。

遠州森町原産の治郎柿
遠州森町は治郎柿の原産地で、江戸時代末期に百姓「治郎(松本)」が太田川の川原で見つけた柿の木を自宅に植えたのが始まりで、その原木は現在も残っています。静岡県の天然記念物に指定されています。毎年秋に皇室に献上している森町の治郎柿は、甘柿の王様として知られています。